【社労士試験対策】労働時間の定義と制度を図表でわかりやすく解説!
今回は労働時間に関して、勉強をしていきたいと思います。
コロナ禍前は、労働時間についてそこまで強く意識されていなかったように思いますが、コロナ禍では在宅勤務が普及し、通勤時間がなくなった分、自分の時間を有効活用できるようになり、生産性が上がったという声も聞かれました。
社労士試験では、労働基準法の「労働時間・休憩・休日」が重要テーマの一つです。特に「労働時間」の理解は、割増賃金や休憩との関係にも直結するため、確実に押さえておきましょう。
労働時間の定義とは?
労働時間とは、「使用者の指揮命令下にある時間」のことです。単に作業している時間だけでなく、準備や待機なども含まれる場合があります。
| 時間区分 | 労働時間に該当するか | 備考 |
|---|---|---|
| 作業中の時間 | ◯ | 当然該当 |
| 待機時間 | ◯ | 上司の指示待ちなど |
| 通勤時間 | ✕ | 原則、労働時間外 |
| 仮眠時間 | △ | 拘束の有無で判断 |
法定労働時間の原則
労働基準法では、法定労働時間は次のとおり定められています。
| 期間 | 時間 |
|---|---|
| 1日 | 8時間以内 |
| 1週間 | 40時間以内 |
これを超えて働かせる場合は、36協定の締結と労基署への届出が必要です。
変形労働時間制とは?
業務の繁忙に応じて、柔軟に労働時間を設定できる制度です。制度ごとに特徴と導入条件があります。
| 制度名 | 特徴 | 導入条件 |
|---|---|---|
| 1か月単位の変形労働時間制 | 1日8時間超も可/週平均40時間以内 | 就業規則・労使協定 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 季節変動等に対応 | 労使協定(届出必要) |
| フレックスタイム制 | 始業・終業時間を労働者が選択 | 週平均40時間を清算 |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 小売・サービス限定 | 特定業種+労使協定 |
頻出ポイント・注意点まとめ
- 変形労働時間制は「週平均40時間以内」が基本。
- 導入には原則として労使協定が必要。
- 36協定なしの残業は違法になる。
社労士試験の過去問より
Q1. 訪問介護事業に使用される者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、使用者が、訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。
A1:◯ 設問のとおり。具体的には、使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一つの利用者から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられる。
Q2. 運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
A2:◯ 該当する。拘束されているため労働時間とみなされる。

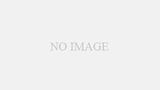
コメント