退職時の証明と金品の返還について
実際、私の勤務先でも退職に関する書類のやり取りは日常的に発生しています。従業員本人と直接やり取りできる場合はスムーズですが、退職代行サービスを利用された場合はそうはいきません。
本人と話せないため、必要性が不明な書類の要望を受けることもあり、対応に手間がかかるのが現場の本音です。
やはり、何事もコミュニケーションが大切ですね。
退職時の証明とは?
「退職時の証明」とは、労働者が退職した際などに、会社(使用者)に対して証明書の発行を求めることができる制度です。次の就職先に提出する書類として利用されます。
労働基準法 第22条の規定
労基法第22条では、以下の2つの義務が定められています。
【1】証明義務の対象内容
労働者が請求した場合、使用者は以下の項目について証明書を交付しなければなりません。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由およびその時期(※退職理由は労働者が請求した場合のみ)
💡 ポイント!
労働者が退職理由の記載を求めない限り、会社が勝手に「懲戒解雇」などと記載してはいけません。
【2】証明書の発行時期
証明書の発行は退職時に限らず、在職中でも可能です。これは、転職活動中の労働者にも配慮した内容になっています。
証明内容で注意すべきこと
実務では、「会社都合退職か、自己都合退職か」が非常に重要です。これは、次のような面に大きく影響します。
- 雇用保険の給付内容
- 退職金の支給要件
- 転職先への印象
そのため、証明書の発行前には労働者と内容をよく確認することが重要です。
金品の返還とは?
続いて「金品の返還」について解説します。
これは、退職時に未払いの給与や立替金などを会社が速やかに支払う義務を定めた制度です。
労働基準法 第23条の規定
【1】返還対象となる金品
以下のような金品が対象になります。
- 未払い賃金(最後の給与など)
- 退職金(支給制度がある場合)
- 有給休暇の未消化分(買い取りが認められる場合)
- 交通費等の立替金
- 労働者の私物(制服・ロッカー内の私物など)
【2】返還期限
⏰ 労働者が請求した場合、会社は7日以内に支払いを完了しなければなりません。
この期限を超えて支払いを怠ると、労働基準法違反となり、行政指導や罰則の対象になる可能性もあります。
社労士試験で問われるポイント
労基法22条・23条は、社労士試験でも頻出の重要項目です。以下の点はしっかり押さえておきましょう。
- 「退職理由」の記載は労働者が請求したときのみ
- 金品の返還は労働者の請求から7日以内
- 金銭だけでなく、立替金や私物も返還対象
- 証明書は退職時だけでなく在職中でも請求可
🔍 模試や過去問では「当然に退職理由を記載しなければならない」などのひっかけ問題も多いので要注意!
実務とリンクさせて理解しよう!
今回紹介した内容は、試験勉強としてだけでなく、実際の人事・労務の現場でも頻繁に出てくるテーマです。
- 労働トラブルの予防
- 適切な退職手続きの運用
- 使用者としての義務理解
こうした実務の視点とセットで学ぶことで、社労士試験の理解が格段に深まります。
まとめ
最後に、本記事の内容をまとめます。
✅ 証明書は労働者が請求した内容のみ記載
✅ 退職理由の記載は、本人が希望したときだけ
✅ 金品は労働者の請求から7日以内に返還
✅ 試験でも実務でも重要な条文!
📝 過去問でチェック!
Q1
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。
→ A:× 不正解
労働基準法第22条1項では、退職理由に関係なく、請求があれば使用者は証明書を交付する義務があります。
Q2
労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。
→ A:× 不正解
これは限定列挙です。したがって、条文に明記された以外の内容については禁止されていません。
💬 さいごに
退職手続きや証明書、金品の返還などは、社労士としても、現場の人事担当者としても避けて通れない重要分野です。明日からも何かと頑張りましょう

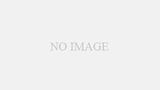
コメント