【労働基準法第20条】突然の「明日から来なくていいよ」はNG?|解雇予告について学ぼう
■ はじめに|法律的にはOKでも、実際はつらい
今回は、「除外(解雇予告が不要なケース)」は取り上げず、基本的な「解雇予告のルール」に絞ってお話しします。
改めて考えてみると、1か月前に解雇を予告すれば法律的には問題ありません。ですが、実際に解雇をされる立場の人にとっては、生活への不安や恐怖は計り知れませんよね。
一方、解雇をする側にとっても、事業継続のためやむを得ない判断という場面もあるはず。だからこそ、このテーマはとても繊細で、法律的知識をしっかり持った上で対応することが重要なのです。
■ 労基法20条とは?「突然クビ」は違法!
労働者を解雇する際、使用者には**「予告義務」**があります。 つまり、**いきなり「明日から来なくていいよ」は原則NG!**なのです。
▼ 条文の概要(第20条第1項)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
このルールは、生活の糧を突然失うことになる労働者に対する、最低限の保護措置として設けられています。
■ 解雇予告の「2つの方法」
労基法第20条では、解雇する場合、次のいずれかを必ず行う必要があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 1. 解雇予告 | 解雇の少なくとも30日前に伝える(口頭でもOK。ただし証拠が残る書面が望ましい) |
| 2. 解雇予告手当 | 解雇日まで30日を下回る場合、不足日数分の「平均賃金」を支払う |
例)「10日後に解雇する」場合は、30日−10日=20日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
■ 平均賃金ってどう計算するの?
ここで言う「平均賃金」とは、原則として、解雇の通知を行う直前3か月間の賃金総額を、総日数で割ったものです。
【計算式】 平均賃金 = 過去3ヶ月間の賃金総額 ÷ 総日数(暦日)
※賞与や臨時手当など、含まれない項目もあるため、細かいルールは社労士試験で要チェックです!
■ 試験対策!よくある引っかけ問題
| 問題 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 使用者は、解雇予告をしないで解雇することができる | ❌ | 原則30日予告か、手当支払いが必要です |
| 労働者に非があると判断すれば、解雇予告は不要 | ❌ | 使用者の独断はNG。労基署長の除外認定が必要です |
| 解雇予告は書面で行う必要がある | ❌ | 法律上は口頭でもOKですが、実務上は書面が望ましいです |
■ 実務での注意点|トラブルを防ぐには?
現場では、解雇予告の扱いがトラブルの火種になることも多いです。次のようなポイントに注意しましょう。
- 解雇理由は必ず文書で明示(トラブル回避)
- 解雇予告期間中に「解雇回避の努力」も行う(配置転換や業務変更など)
- 労働者との対話を丁寧に行い、感情的な対立を防ぐ
■ 過去問チェック!
Q1: 使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。
A1:× 労基法20条1項ただし書 → 労働者の帰責性が軽微な場合は、原則として、解雇予告の除外認定には該当しない。したがって、解雇予告及び解雇予告手当の支払い義務がある。
Q2: 使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。
A2:○ 昭和24年基収1701号 → 使用者の即時解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立するまでの間、休業手当を支払わなければならない。
■ まとめ|「解雇の予告」は労使の信頼を守るルール
労基法第20条は、労働者の生活を守るため、最低限の準備期間または補償を与えることを義務付けた重要な条文です。
次は「解雇予告の除外」について勉強をしていきたいと思います。

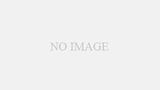
コメント