強制貯金の禁止とは?
今回は、労働基準法の中でも意外と見落としがちな「強制貯金の禁止」について勉強していきます。試験対策にもなるだけでなく、実務や日常生活にも役立つ知識なので、ぜひ最後まで読んでみてください!
強制貯金の禁止とは?
労働基準法第18条では、以下のように定められています。
〔第十八条〕使用者は、労働者に対して貯金を強制してはならない。
簡単に言えば、「会社が従業員に対して無理やり貯金させることはダメですよ」というルールです。貯金というのは本来、個人の自由意思に基づくものであって、会社が強制してはいけないという趣旨です。
どんな行為が「強制貯金」に当たるの?
それでは、どこまでが「強制」なのでしょうか?たとえば以下のようなケースが問題になります。
❌ 例1:給与天引きで一定額を貯金させる
「入社したら毎月1万円を会社指定の口座に強制的に貯金させます」
これは典型的な違反です。本人の同意があっても「強制」であればNGになります。
❌ 例2:社内制度として貯金を義務化
「社員貯金制度に加入しないと賞与が減額される」
このような事実上の強制も違反とみなされる可能性があります。
✅ 例外:自主的な貯金制度
「社員が任意で加入できる財形貯蓄制度」
こういったものはOKです。本人が自由意思で選択し、途中脱退も自由であることが前提になります。
なぜ強制貯金が禁止されているの?
この規定の背景には、労働者の経済的自由を守るという目的があります。
貯金とは本来、収入の中から自分の判断で自由に行うべきものです。会社が強制することで、労働者の生活に悪影響が出る可能性もあるため、国はそれを制限しています。
また、過去には企業が労働者の賃金から一方的に天引きして社内貯金制度に入れ、そのお金を勝手に運用していた事例もありました。こうした問題を防ぐための法律でもあるのです。
労働基準法以外にも関係するルール
◆ 賃金全額払いの原則(労基法第24条)
労働者への支払いは原則「全額、直接、通貨で」支払わなければなりません。強制貯金はこのルールにも違反する可能性があります。
◆ 労働契約法や民法の視点からもNG
強制的な天引きや契約は、労働契約の自由や個人の財産権を侵害する行為とみなされ、無効とされることもあります。
試験対策ポイント!ここをチェック
社労士試験では、以下の点が問われやすいです:
- 「本人の同意があっても強制ならNG」
- 「任意の財形貯蓄制度などは例外としてOK」
- 「違反すると労基法違反で是正勧告の対象になる」
記述式というよりも、選択式や択一式で引っかけ問題として出題されることが多いので、**「自主性があるかどうか」**をしっかり見極めましょう。
実務での注意点:制度設計と運用の工夫
実務の場では、福利厚生の一環として貯金制度を導入したいと考える企業もあります。その場合は、以下のようなポイントを守りましょう。
- 完全任意であること(加入・脱退の自由)
- 同意書をとって明確に意思確認
- 担保として給与を差し押さえるような条項は入れない
- 他の制度(社宅や貸付金)と絡めて事実上の強制にしない
制度を設計する側も、使う側も、「これは本当に“任意”か?」を常に意識することが大切です。
まとめ:貯金は自由!ルールを守って健全な職場づくりを
「強制貯金の禁止」は、シンプルなルールですが、実務の中では意外とグレーな運用をされてしまうこともあります。
過去問
Q1:使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
A1:× 労基法18条1項
労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることはできない。
Q2:中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第18条の禁止する強制貯蓄には該当しない。
A2:× 労基法18条 昭和25年基収2048号
設問の例は、強制貯蓄に該当する。
今回はこんな感じで、また明日以降も頑張っていきます!!

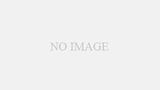
コメント