少しバタついていましたが、また引き続き頑張っていこうかと思います。
賠償予定の禁止(労働基準法第16条)とは?
労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定められています。
これは、労働者の自由な意思を守り、不当な制約から保護するための重要な規定です。
1. 趣旨と目的
労働者は、労働契約を結んだ後も、合理的な理由があれば退職することができます。しかし、雇用主が「退職したら違約金を支払え」とか「仕事でミスをしたらあらかじめ定めた額の賠償を負え」とする契約を結ばせると、労働者の自由が著しく制限されてしまいます。
そのため、法律であらかじめ違約金や賠償額を決めることを禁止しています。
2. 違約金や損害賠償の予定とは?
(1) 違約金の禁止
- 退職時に違約金を請求する契約
- 早期退職の場合に罰金を課す契約
(2) 損害賠償の予定の禁止
- 「退職したら○○万円を支払う」といった契約
- 「仕事上のミスに対して、必ず○○円の賠償をする」などの契約
→ これらはすべて無効です。
3. 「賠償予定の禁止」と「実際の損害賠償請求」の違い
労働基準法第16条は、あらかじめ損害額を決めることを禁止しています。しかし、実際に労働者が会社に損害を与えた場合、実際の損害額を根拠に損害賠償請求をすることは可能です。
例えば、
✅ OK(合法):「従業員が故意または重大な過失で会社に損害を与えたため、実際に発生した損害額を請求する」
❌ NG(違法):「どんな場合でも10万円を賠償する契約を結ばせる」
4. 賠償予定の禁止に違反した場合
もしも使用者が違約金や損害賠償を予定する契約を結んだ場合、その契約は無効になります。さらに、労働基準法第120条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
5. 具体例と判例
(1) 具体例
- 例1:退職する場合には「研修費用○○万円を返還する」 → NG(一律の返還義務を負わせる契約は無効)
- 例2:会社の機密情報を流出させ、実際に1,000万円の損害が発生 → OK(実損害がある場合、裁判で認められる可能性あり)
(2) 判例(フジ興産事件・最高裁判決)
企業が労働者に対して「退職時に研修費用を返還させる契約」を結んでいたが、最高裁判所は「一律に返還を求めるのは賠償予定の禁止に違反する」として無効と判断しました。
6. まとめ
- 労働基準法第16条は、労働者の自由を守るために「違約金・損害賠償の予定」を禁止している。
- 実際に損害が発生した場合は、損害額に基づいて請求できるが、事前に決めることは違法。
- 違反した場合は無効となり、罰則の対象になる。
実際の過去問
Q1:労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
A1:○ 労基法16条
設問のとおり。民法は契約自由の原則に基づき、違約金を定めることを認めているが、労働関係にお
いては労働者の足留策に利用され身分的拘束を伴うこととなるので、これを民法の特別法として禁止
したものである。
Q2:債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。
A2:× 労基法16条 昭和22年発基17号
禁止されているのは「損害賠償額の予定」であり、額について記載がなければ違反にはならない。
Q3:使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
A3:× 労基法16条
損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
今日も1日お疲れ様です。
明日以降も頑張りましょう

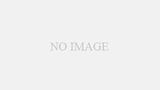
コメント