今回は労働基準法における、中間搾取に関して勉強をしていこうと思います。
1. 「中間搾取の排除」とは?
「中間搾取」とは、労働者が働いた対価の一部を、不当に第三者が搾取することを指します。
たとえば、派遣業者やブローカーが不当な手数料を取り、労働者の賃金が適正に支払われないケースが該当します。
このような中間搾取を防ぐために、労働基準法では**「労働者供給事業の禁止」(労働基準法第6条)**を定めています。
2. 労働基準法第6条の条文とその趣旨
(条文)
何人も、他人の就業に介入して利益を得てはならない。ただし、法律に基づいて行われる場合は、この限りでない。
この条文は、
- 労働者を商品として売買するような行為を禁止する
- 不当な仲介によって労働者が搾取されることを防ぐ
ことを目的としています。
3. なぜ中間搾取が禁止されているのか?
歴史的背景と現代の問題の両方から、中間搾取禁止の重要性を解説します。
(1) 歴史的背景
- 戦前の人身売買的労働供給
- 日本では戦前、労働者の仲介業者(口入れ屋)や人夫請負業が横行し、低賃金・劣悪な労働環境が問題になっていました。
- こうした状況を是正するため、戦後の労働基準法で「労働者供給事業の禁止」が明文化されました。
- 国際基準の影響
- ILO(国際労働機関)の「強制労働条約」でも、労働者の自由な就労を阻害する不当な仲介は禁止されています。
(2) 現代における問題
現代でも、以下のような形で中間搾取の問題が発生しています。
- 悪質な派遣業者・ブローカーによる不当なピンハネ
- 「紹介料」や「登録料」として高額な手数料を取り、労働者の賃金を圧迫する。
- 特に外国人労働者に対して高額な手数料を課す事例が多い。
- 偽装請負
- 本来、労働者派遣であるにもかかわらず、「請負契約」として偽装し、法規制を回避する企業がある。
- 偽装請負の場合、労働者が不当な労働環境に置かれることが多い。
4. 労働基準法第6条が禁止する「中間搾取」の具体例
(1) 労働者供給事業の禁止
労働基準法第6条では、労働者を供給すること自体を原則として禁止しています。
禁止されるケース
- A社がB社に労働者を送り込み、A社が労働者の賃金の一部を搾取する(違法な労働者供給)
- ブローカーが仕事を紹介する代わりに、労働者から手数料を取る(不当な仲介料)
許可されるケース(例外)
- 職業紹介事業(有料・無料)
- 厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介業者は、適正な手数料を受け取ることができる。
- 例:ハローワーク、民間の転職エージェント
- 労働者派遣事業
- 派遣業は「労働者供給」と似ているが、派遣元と派遣先の間で契約が明確になっており、法律で適正に管理されている。
- 労働者派遣法に基づき、労働条件が適正に保たれる必要がある。
(2) 偽装請負の禁止
- 「請負契約」に見せかけて、実際には派遣労働を行うケースは違法。
- 企業が直接指示・監督する場合、請負ではなく「労働者派遣」となるため、派遣法に基づく許可が必要。
5. 中間搾取を行った場合の罰則
労働基準法第6条に違反した場合、使用者や仲介業者には厳しい罰則が科されます。
(1) 刑事罰
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(労働基準法第119条)
(2) 行政指導・営業停止
- 労働基準監督署が調査を行い、**是正勧告・行政処分(事業停止命令)**を行うことがある。
- 悪質な場合は、許可取消や事業停止処分が下される。
6. 現代における違法な中間搾取の事例
(1) 外国人技能実習生の搾取問題
- 実習生の母国でブローカーが高額な手数料を徴収し、借金を抱えたまま日本で働かされる。
- 賃金の一部を実習先が搾取し、適正な給与が支払われない。
- → 労働基準法違反の可能性が高く、政府が監視を強化している。
(2) 違法な派遣・紹介業者の横行
- 求人サイトやSNSを通じて、「仕事を紹介する」と言いながら、紹介料をピンハネする悪質業者が存在。
- 労働者が適正な賃金を受け取れず、法的保護も受けられない。
7. 企業が適正に運営するためのポイント
(1) 適正な職業紹介・派遣業の運営
- 厚生労働省の許可を取得し、適正な手数料で職業紹介を行う。
- 派遣労働者の賃金や労働条件を適正に管理する。
(2) 労働者の権利を守るための社内監査
- 外部の仲介業者を利用する場合、その業者が適正な手続きを踏んでいるか確認する。
- 労働基準監督署やハローワークに相談できる窓口を設置する。
8. まとめ
- 労働基準法第6条では、中間搾取を禁止し、労働者の賃金を適正に確保することを目的としている。
- 違法な労働者供給事業や偽装請負は処罰の対象となる。
- 現代でも、外国人技能実習生の搾取や違法な派遣業者の問題が発生している。
- 適正な職業紹介や派遣事業の運営が求められる。
実際の過去問
Q1:労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
Q2:労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。
A1:× 労基法6条 昭和23年基発381号
違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、個人、団体又は公人たると
私人たるとを問わない。したがって、公務員であっても、違反行為の主体となり得る。
A2:× 労基法6条 昭和23年基発381号
反覆継続して利益を得る意思があれば、1回の行為であっても「業」とされ、規制対象となる。「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称であるかを問わず、また有形無形であるかを問わない。
本日はここまでにします。

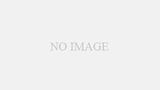
コメント