先日の続きでより労働基準法、基本原則の箇所を掘り下げていければと思います。
2-2. 強行法規としての性格(第13条)
労働基準法は強行法規であり、労基法に違反する労働契約の条項は無効となります。そのため、労働契約において労働者に不利な内容があった場合でも、法律の基準が適用されます。
これは、労働者の権利保護を目的とした重要な規定であり、例えば賃金、労働時間、休日などの条件が法律の基準を下回る場合、その部分の契約は無効となり、労基法の定める基準が適用されます。
また、労働契約が一部無効となった場合でも、契約全体が無効になるわけではなく、無効部分のみが排除され、残りの契約内容は有効に存続するのが原則です。
実務においては、企業が労働者と合意の上で労基法の基準を下回る契約を結ぶことがあっても、それは法的に認められず、労働者が不利益を被ることがないようになっています。
2-3. 均等待遇(第3条)
労基法第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、労働条件について差別してはならない」と定められています。これは、労働者が公平な待遇を受けられるようにするための規定です。
この規定の目的は、すべての労働者が平等な条件のもとで働くことができるようにすることです。特に、外国人労働者、特定の宗教を信仰する労働者、社会的地位の違い(例えば、家庭環境や学歴など)による不当な待遇の差を防ぐ役割を果たします。
(1)適用範囲と具体例
本条は、賃金、労働時間、昇進、福利厚生、解雇など、すべての労働条件に適用されます。たとえば、以下のようなケースが禁止されます。
- 外国籍を理由に昇進の機会を制限する
- 宗教的信条を理由に特定の職種への配属を拒否する
- 出身家庭の経済状況を理由に低賃金で雇用する
(2)違反時の対応と判例
もし企業が本条に違反した場合、労働者は労働基準監督署に申告することができます。また、裁判においても、違反が認められた場合には、企業に対する是正命令や損害賠償請求が可能となります。
例えば、過去の判例では、特定の国籍の労働者に対して日本人労働者より低い賃金を支払っていた事例で、裁判所が企業に対し賃金差額の支払いを命じたケースがあります。
(3)企業の対応策
企業は、均等待遇の原則を確実に守るために、以下のような対策を取る必要があります。
- 労働条件の決定基準を明確化し、客観的な評価制度を導入する
- 社員教育を行い、差別的な取り扱いが行われないようにする
- 定期的な社内監査を行い、公平な労働環境を確保する
このように、均等待遇の原則は単なる理念ではなく、具体的な運用が求められる重要な規定です。
実際の問題実例
Q1:労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
A1:× 労基法3条 昭和63年基発150号
後半が誤り。「その他の労働条件」には、解雇についての条件も含まれる。
Q2:労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
A2:× 労基法3条
労基法3条(均等待遇)では、「性別」を理由とした差別的取扱いは規定されていない。
Q3:労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
A3:○ 最判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)
設問のとおり。労基法3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、「雇入れにおける差別
は含まれない」とするのが最高裁の判例とされ「企業者が特定の思想、信条を有する者をその故をも
って雇い入れることを拒んでも、それを当然に、違法とすることはできない」とされている。
今日もお疲れ様でした。明日以降も頑張りましょう!

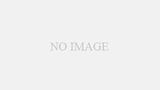
コメント