社労士頑張れるようにアウトプットしていこうかと思います。
まずは基本的な部分の労働基準法に関して、基本原則部分箇所を勉強していこうかと思います。
1. 労働基準法とは?
労働基準法(以下「労基法」)は、労働者の権利を守るために定められた日本の法律です。労働条件の最低基準を定めており、使用者(企業)はこれを下回る条件で労働者と契約を結ぶことはできません。社労士試験でも頻出の法律です。
2. 労働基準法の基本原則
2-1. 労働条件の最低基準の確保(第1条)
労基法第1条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない」と定めています。これは、労働者の生活を守るために、最低限の労働条件を保障するという基本的な理念です。
(1)労働条件の最低基準とは?
労基法1条の趣旨は、労働者が経済的・社会的に安定した生活を送れるよう、最低限の労働条件を確保することにあります。これは、労働時間、賃金、休暇、安全衛生など、あらゆる労働条件に適用されます。
(2)労働条件の向上を目指す
単に最低基準を維持するだけでなく、社会・経済の発展に伴い、労働条件の向上が図られるべきであるとされています。これは、労基法第2条とも関連し、労使対等の原則のもと、労働条件の改善を促進する目的があります。
(3)関連判例と実務上の影響
裁判例では、労働条件が労基法の基準を下回る場合、無効と判断されることが多いです。たとえば、最低賃金以下の賃金設定や、違法な長時間労働を強制する契約は無効となり、法定基準が適用されます。
2-2. 強行法規としての性格(第13条)
労働基準法は強行法規であり、労基法に違反する労働契約の条項は無効となります。そのため、労働契約において労働者に不利な内容があった場合でも、法律の基準が適用されます。
2-3. 均等待遇(第3条)
労基法第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、労働条件について差別してはならない」と定められています。これは、労働者が公平な待遇を受けられるようにするための規定です。
2-4. 男女同一賃金の原則(第4条)
労基法第4条は、同一の仕事をしている場合には、男女間で賃金の差別をしてはならないと定めています。これにより、男女の公平な賃金体系を確保することが求められます。
2-5. 公民権行使の保障(第7条)
労働者は、選挙権などの公民権を行使するために必要な時間を請求でき、使用者はこれを拒んではなりません。この規定により、労働者の市民としての権利が守られています。
2-6. 労働条件の向上(第2条)
労働基準法第2条では、「労働条件は労使対等の原則に基づいて決定されるべきであり、労働者および使用者は、労働条件の向上を図るよう努めなければならない」とされています。これは、単に法律の最低基準を守るだけでなく、労働環境の継続的な改善が求められることを意味します。
2-7. 労働契約の公正な締結(第15条)
労働契約を締結する際には、使用者は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。特に、賃金や労働時間、業務内容などの重要な事項については、書面(または電子媒体)で通知する必要があります。
ここまで学んだ事での過去問
Q1:労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
A1:○ 労基法1条1項
設問のとおり。人たるに値する生活がキーワード。選択式でも出題されている。
Q2:労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
A2:× 労基法1条 昭和22年基発401号
後半が誤り。標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念による。

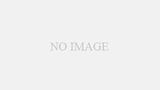
コメント